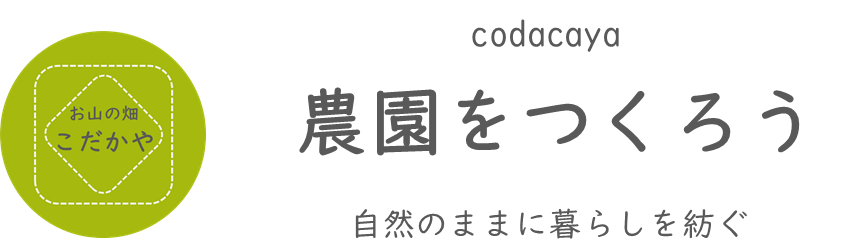綿の木は、1年草。
収穫後は、根っこから抜き取ります。
数が多いと時間はかかりますが、抜く力はそんなに必要ではありません。
むんずっと幹をつかめば、ポンッと抜けます。
まだ綿の実がはじけず残ったままだけど
12月上旬には、まだ葉が緑色だった綿木。

暖かいながらも、少しずつ冬を迎えています。
12月中旬は、お山の木々は緑青々としていますが、綿木の葉は緑色から茶色へと変わってきました。
12月下旬になると、枝も葉も実も茶色く枯れ始めています。
まだまだ実がたくさんついたまま、はじけていない。

日照時間が短かったのか、
寒さに弱いからなのか、
累積温度が足りなかったのか、
霜にあたってしまったからなのか、
原因はいくつもあると思います。
はじけきれないでいる綿の実は、変色していたり、カビが生えたりしています。

途中まで開いて、その後はカチカチに固まってしまう実もありました。

このまま放っておいても、もう綿ははじけない気がします。
元気そうな実は摘んで、綿木を抜くことにしました。
摘んだ実は、部屋の窓際で天日干しにしています。
徐々にはじけて、綿がふくらんできました。

綿木を抜いたら蝉の幼虫が飛び出てきた
根っこの近くをつかんで、ちょっとだけ力を入れて抜きます。

スポンと抜けます。

一緒に何か飛び出してきました。
蝉の幼虫ですね。
寒い冬の間も、数年かけて土の中で育っているそうですね。
掘り起こしてしまって、ごめんなさい。
土の中に戻っていただきました。
抜いた洋綿の木の根っこは、主根から側根が広がっていました。
といっても、そんなにびっしりと根っこが生えているわけでもありません。

小石の混ざった粘土質の土。
根が広がろうとすると小石にあたります。
粘土質の土は表層土はやわらかいけれど、20センチほど下からは固いので、深く伸びていくことはできなかったかもしれません。
背丈ほどの綿木が、ちょっと頼りなさそうな根っこで支えられて立っていました。
和綿はもっと根っこが少なくて、よくぞ立ってくれていたと思います。
並べてみると、太さが倍くらい違います。

左側が洋綿、右側が和綿です。
洋綿のほうが和綿より太いし、重いです。
洋綿は、台風で倒れてしまった木が数本あります。
和綿のほうは、こんなに細いのに台風にも耐えて、折れた木はひとつもありませんでした。
なんというか、しなやかな弾力があるように思います。
抜いた綿木は、畑の端に積んでおきます。

乾燥後、燃やして灰にすれば、アルカリ性の肥料になります。
でも、野焼きはやめておきましょう。
お山の畑では、自然に朽ちるのを待っています。
4年前に開墾して摘んだ草木は、4年かけて堆肥になりました。
積んでおいた場所の土はフカフカです。
この堆肥を畑に使います。
綿木引き後の畑にニンニクを植える
綿木引きをして、2019年の綿栽培は終わりです。
来年のために、綿のコンパニオンプランツと言われているニンニクを綿木の間に植えつけています。
葉が育ってきましたが、なんだか弱々しい。

土を病気から守る、土を元気にする役割があるらしいのですが。
でも、きっと育ってくれます。
来年の春まで、草草が根を張り、土を耕してニンニクとともに綿畑を守ってくれることでしょう。
3年目の綿栽培は、イノシシに何回も踏み荒らされ、台風が何度も直撃し、残った綿木は多くありませんでした。
それでも、たくさんの実をつけてくれました。
かわいい綿のできる様子を見るだけで、やさしい気持ちになるし、ふわふわもこもこした手触りに和みます。
いろいろと反省もあり、次年に向けて実験したいこともあります。
基本的な綿の栽培方法は、調べると知ることはできます。
自然のままにつくろうとすると、環境条件が異なっているからか、調べたようにはならないところもあります。
花色の変化や実の大きさ、木色の違い、ハマキムシ大量発生の原因など、もっと観察したいことがたくさんあります。
綿の国内自給を増やそうとか、環境問題について考えようとか、大きな目標はありません。
お山の綿栽培の様子をただ記録して書いているだけですが、おもしろそうでしょう?
数週間後、畑の端に積んでいた綿木に残っていた綿の実がはじけていました。

手のひらに冬の綿。

雪は、まだ降っていないです。